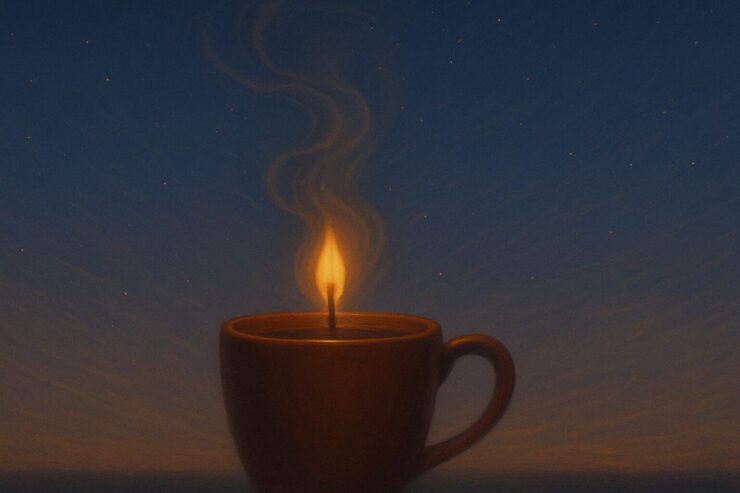気づけば一日が終わっていて、
「結局なにも進んでない…」
そんな日が続くと、時間の使い方そのものを疑いたくなりますよね。
でも実は、時間管理って「根性」でなんとかするものではありません。
もっと静かで、もっとやさしい構造で整えたほうが、毎日は驚くほど軽くなります。
時間が足りないのではなく、
何を優先するかを選べていないだけかもしれません。
そのズレをそっと直すだけで、焦りは消えていきます。
このガイドは、
・やりたいことが多すぎる
・時間が足りなくて毎日焦る
・集中はできるのに、続かない
そんな人に向けた「再定義」型の時間術です。
必要なのは、難しいアプリでも、完璧な計画でもありません。
今日からできる小さな選択の整え方を、3つだけお伝えします。
時間の流れ方は、きみの意志で必ず変えられます。
目次
なぜ時間が足りないと感じるのか
時間が足りない。
そう感じる瞬間は、決まって「やることが多すぎる日」だけではありません。
むしろ、やる気があるのに手がつかない日、気づけば時間が溶けていた日に、
より強く訪れる感覚です。
これは能力不足でもだらしなさでもありません。
「時間感覚」と「選択」そのものにズレが生まれているだけです。
1|現代人の「時間の錯覚」は、情報量が引き起こす
スマホを開けば、新しい情報が流れ込み続ける。
SNSで友人の成果も見え、ニュースは絶え間なく更新され、
通知は数分単位で鳴り続ける。
この環境では、
「やるべきこと」が増えたように錯覚しやすくなります。
本当は今日やる必要のないことまで、
今すぐやらないと遅れる気がするという状態を引き起こすからです。
時間の不足感は、
実際の「タスク量」ではなく、
情報に対する焦りのほうが強く作用すると言われています。
2|「決められない」が一番時間を奪う
やることを選ぶだけで、脳は大量のエネルギーを使います。
これが「決断疲れ」。
同じ30分でも、
・タスクを一つ選ぶまでの30分
・作業を続ける30分
では、体感がまったく違う。
前者は「消耗感」。
後者は「進んでいる感覚」。
多くの人が時間を失っていく原因は、
タスクそのものではなく、
「選ぶ」までの迷いの時間なんです。
しかも迷う時間ほど、自己嫌悪を誘発しやすく、
「今日も進められなかった…」という負の感情が蓄積されます。
3|完璧主義が、時間の密度を破壊する
いまの若い世代ほど、
「どうせやるなら完璧にしたい」
という欲求が強いと言われています。
これは悪いことではありません。
でも、完璧主義は時間管理においては大きな罠になります。
完璧にやろうとすると
→ 最初の一歩が重くなる
→ 手をつけられない
→ 未着手が増える
→ 「時間がない」という結論になる
このループが無意識に起こります。
実際のところ、
完璧である必要があるタスクは、
全体の一割もないにも関わらず、
人は全てに同じ基準を持ち込んでしまうのです。
時間の不足感は
「自分がまだ動けていない」という焦りが膨らんだ結果とも言えます。
4|時間の使い方は「性格」ではなく「構造」で決まる
多くの人が「時間の使い方が下手だ」と思い込みますが、
実は性格と時間管理能力には相関性がほとんどないと言われています。
本当に影響するのは、
タスクの置き方、選び方、区切り方。
つまり、
性格ではなく「構造」です。
・選択肢が多すぎる
・優先順位を決める基準がない
・行動の粒度が大きすぎる
・やらなくていいことの棚卸しができていない
・未来の自分に丸投げしてしまう癖がある
これらのどれかがあるだけで、
どんな人でも簡単に「時間が足りない人」になります。
逆に言えば、
構造を調整するだけで、
誰でも「時間がある人」へ変われるのです。
5|時間不足は自己否定を呼びやすい
やることが進まない日、
人は「意欲」ではなく「自分そのもの」を否定しやすくなります。
・自分はダメだ
・うまくできない
・時間をうまく使えない
・他の人はもっとできている
本当は逆なんです。
進めない日は、
心と身体が余白を必要としているサイン。
時間管理が破綻しているのではなく、
気持ちの回復が追いついていないだけ。
この事実を知るだけで、
時間管理の苦しさは静かにほどけていきます。
6|「時間が足りない」気持ちには名前をつけられる
心理学では、
この状態を「時間ストレス」と呼びます。
・未来に追いつけない焦り
・選べないことによる消耗
・進んでいない感による不安
・やれていない罪悪感
これらが混ざりあって、
まるで時間が溶けていくような感覚をつくりだします。
逆に言えば、
これらの正体を理解することで、
時間管理は驚くほど優しくなる。
時間の問題ではなく、
気持ちと選択の問題だったと気づいた瞬間、
視界が変わります。
時間管理=「選択の整理」である
時間管理と言うと、
多くの人は「スケジュール帳を整える」「アプリで予定を管理する」
そんなイメージを思い浮かべます。
でも、本質はまったく別のところにあります。
時間管理とは
どの選択を残すかを決める作業
なんです。
つまり、時間そのものをいじるのではなく、
自分が何に時間を渡すかを決める技術です。
1|時間管理の第一歩は「足し算」ではなく「引き算」
ToDoを増やせば増やすほど、
時間は管理しづらくなっていきます。
本来は
・やらなくていいこと
・やる必要のないこと
・先送りしても問題ないこと
・他の人でもできること
を切り分けるところから始まるのに、
多くの人は「どう詰め込むか」ばかり考えてしまう。
でも、詰め込むほど
タスク同士がぶつかり、
どれも中途半端に進まないという状態を生みます。
時間管理の本質は
タスクの量ではなく、選択の質。
ここが整わない限り、どんなアプリも仕組みも効果を出せません。
2|優先順位は「重要度」ではなく「意志」で決める
よくある間違いは、
「重要度でタスクを並べ替える」こと。
もちろん重要度は必要ですが、
日常生活では高度な判断よりも
意志の向きが優先されることの方が多い。
人は「重要だけど気が乗らないこと」を先にやるほど
エネルギーを消耗し、
時間の密度が崩れます。
逆に、
意志と一致するタスクから着手すると、
時間は濃く、軽やかに流れ始める。
これは心理学でも証明されていて、
意志とタスクの一致度が高いほど、
短時間で高い没入が得られると言われています。
つまり、優先順位は
「重大かどうか」ではなく
今日の自分が動ける順
で決める方が現実的なのです。
3|やることの粒度が大きすぎると、選択は鈍る
時間管理に悩む人の多くは、
タスクの粒度が大きすぎます。
例:
・ブログを書く
・副業をする
・片付ける
・勉強する
・企画を考える
これはすべてプロジェクト名であり、
タスクではありません。
プロジェクトに取りかかろうとすると、
脳が勝手に
「どこからやるんだっけ…?」
という迷いのプロセスを挟みます。
その結果、
開始までの時間が伸び、
「時間がない」という感覚が生まれます。
粒度を小さくすれば、
選択も行動も一瞬で軽くなります。
例:
・3行だけ書く
・10分だけ下調べをする
・机の上だけ片付ける
・本を1ページ読む
・企画のタイトルだけ書く
この小ささが、
選択しなくても動ける時間をつくります。
4|選択が整理されると、時間は増えたように感じる
時間は絶対的なものに見えて、
実は「主観」で大きく変化します。
同じ1時間でも
・選択が定まっていて集中できる1時間
・迷いが続き不安が混じった1時間
では、体感速度が全く違う。
前者は「進んだ時間」。
後者は「失われた時間」。
時間の進み方を変える鍵は
選ぶものを減らし、残したものに集中することです。
すると、
タスクの密度が上がり、
「時間が増えた」と錯覚できるほどの余裕が生まれます。
人は「増えた感覚」を得たときに、
行動が自然と増えます。
これが、時間管理がうまく回り始める最初の兆し。
5|時間管理の核心は「自分の現在地」を知ること
選択の整理がうまく働くのは、
自分の現在地を把握できているから。
・今の自分は疲れている?
・集中できる状態?
・5分なら動ける?
・今日は重いタスクは向いていない?
こうした自己観察ができる人は、
タスクを正しく選べます。
逆に、
現在地が曖昧なまま動こうとすると、
やることの難易度と気分が一致しないため、
時間が「重く」なります。
時間術とは、
自己理解術でもある。
6|選択の整理を始めると、心が軽くなる
何を選ぶかだけでなく、
何を選ばないかを決めることは
心の負担を確実に減らします。
・やらなくてもいいことを手放す
・SNSのチェック回数を減らす
・やらない日をつくる
・優先度の低い予定を断る
これらは全て「心を守る時間管理」です。
優先順位の整理は、
自己肯定感を回復させ、
やれる自分を取り戻すための行為でもあります。
時間が増える人の行動心理とは?
「時間をうまく使える人」と「いつも追われている人」。
この差は、才能でも、努力量でもありません。
むしろ、
行動を始めるまでの心理と習慣 によってほぼ決まっています。
1|時間が増える人は「やることを増やさない」
多くの人は、
時間管理の改善=タスク管理の強化
だと考えます。
けれど、本当に時間が増えていく人たちは、
真逆のことをしています。
それは
やらないことを先に決めておく
ということ。
この習慣がある人は、
選択肢が絞られているため、
タスクに迷う時間が圧倒的に減ります。
やらないことを決める行為は、
「意思力の節約」
「過剰な情報から自分を守る」
この二つを同時に叶えてくれます。
時間術の基盤は、
足し算ではなく引き算。
ここが揺るがない人ほど、毎日が軽くなっていきます。
2|動ける人の行動心理「着手のハードルを限界まで下げる」
人が行動できなくなる最大の原因は、
タスクの開始コストが高すぎること。
この開始コストを下げる具体的手法は、
実はとても単純です。
・3分だけやる
・最初の1行だけ書く
・机に座るだけ
・アプリを開くだけ
この最初の一挙動ができるかどうかで、
その日の集中がほぼ決まります。
脳科学では
「一度行動すると、脳の抵抗が激減する」
ことがわかっています。
はじめの3分が越えられると、
その後に30分でも60分でも自然につながる理由は、
脳のブレーキが弱まるためです。
つまり、
「短く始める」ことが、結果的に「長く続く」近道。
3|時間が増える人は「選択を固定」している
仕事や副業が忙しいのに、なぜか時間を確保できる人は、
一度決めた行動を自動化しています。
・朝は同じルーティン
・使うアプリを一本化
・迷いがちな作業は「曜日」で固定
・15分単位の「定番タスク」をつくる
これらは
「意思決定の節約」
という心理技術です。
意思決定にはエネルギーが使われるため、
選択が多すぎると疲れてしまう。
逆に、選択が固定されていると、
なんの意識もなく行動できるようになり、
結果的に時間が浮く。
時間が増える人は、
自由に動いているようで、
実は「選択肢を減らしている」んです。
4|時間が減っていく人は「気分に依存」している
気分が乗らないと動けない。
やりたくなってから始める。
完璧にしたいから、調子の良い日にまとめてやる。
これは、多くの人が陥る落とし穴です。
気分が整う日を待つほど、
行動のリズムは乱れ、
取り戻すための時間が必要になる。
時間管理の上手な人は、
気分が乗らないときに
小さく動く技術
を持っています。
・1分だけ
・1ページだけ
・メールを1通返すだけ
・机を拭くだけ
この「最小単位の行動」が積み重なることで、
気分の波が大きい日でも、
時間を失わなくなる。
気分任せにしない人は、
感情に振り回されずに進める構造を持っているのです。
5|継続する人の秘密は「予測可能な疲れ」
集中すること自体が悪いわけではありません。
問題は、予測できない疲れにやられてしまうこと。
集中した時間が突然切れると、
脳と体はその落差に驚き、
一気に消耗します。
時間が増える人は、
「疲れを予測して、先に休む」
という技術を自然に使っています。
・45分作業 → 5分休む
・朝の集中ブロックは短め
・午後は軽タスクに分散
・夜は整える時間として回復に充てる
このように、
疲れを前倒しでコントロールしている。
人間は予測可能なものには強い。
予測不能なものに弱い。
この特性を理解している人は、時間の流れ方に乱れが出ません。
6|「時間が増える行動心理」のまとめ
時間が増えていく人の共通点は、
能力や天才性ではなく
行動の敷居を下げる心理習慣を持っていること。
・やらないことを先に決める
・3分で始める
・行動の選択肢を固定する
・気分に頼らない
・疲れを予測して前倒しで整える
このどれもが、
今日からすぐに真似できる微細な技術です。
時間は、使い方で増減するのではなく、
行動の心理構造で変わる。
ぼくの時間管理構造
時間管理は、スケジュールより自分の内側を扱う行為です。
だからこそ、他の誰かの時間術よりも、
「ぼくがどんな構造で日々を組んでいるのか」
を一度具体的に言語化してみようと思います。
ぼく自身は、仕事、創作、世界観構築、読書、企画、SEO、文章、キャラ運用。
扱う領域が多いぶん、普通の時間管理ではとても回りません。
「どう整えているの?」
とよく聞かれるのですが、その答えは簡単で、
気分ではなく構造で動く
これだけです。
ここでは、その構造を読者にも再現できる形で書き残していきます。
1|ぼくの朝は「時間の向きを決める時間」
朝起きてすぐ、ぼくは作業を始めません。
やることを増やす前に、まず今日の方向を静かに見る。
ぼくが朝にやることは三つだけです。
- 今日の自分の「調子」を短く観察
- 動けるタスクの難易度をざっくり分ける
- 一番最初にやることを決める
ここで決めるのは、予定ではなく
時間の向き。
今日は深い思考に向いているか、
軽いタスクのほうが進む日か。
文章のエンジンが温まりそうか、
下調べのほうが向いているか。
調子とタスクが一致している日は、驚くほど時間が伸びます。
逆に、調子と合わないタスクを置くと、
その日一日の流れが重くなる。
ぼくが朝にしていることは、
今日の自分と世界の接続点を探す行為です。
2|ぼくの「集中ブロック」は長くない
ぼくは長時間集中するほうではありません。
むしろ、短い集中をいくつも積んでいくタイプ。
集中ブロックは
20分〜40分 が基本。
理由は単純で、
創作も構造設計も、短いスパンの方が思考の切れ味が保てるからです。
集中→小休憩→集中
このリズムを繰り返すと、
時間の密度が自然と保たれます。
ぼくの創作や構造設計がブレないのは、
才能ではなく、
短時間の集中を積み上げているからなんです。
3|「世界観作業」と「実務作業」は、混ぜない
ぼくは、タスクを二種類に分けています。
- 世界観系タスク(想像・構造・物語・キャラ)
- 実務系タスク(書く・整える・調べる・設計する)
この二つは、脳の使い方がまったく違うので、
混ざるとパフォーマンスが落ちます。
ぼくは必ず
「どちらの脳を使う時間か」
を先に決めて作業に入ります。
これは誰でも再現できる技術で、
世界観系の日には深く想像できるし、
実務系の日には驚くほど量が進む。
時間を増やす秘訣は、
脳のモードを明確に分けておくこと。
4|ぼくの「夜の時間」は、切り替えの儀式
夜は、作業を進める時間ではありません。
ぼくにとって夜は、
「自分を回復させて、明日を準備する時間」です。
小さな儀式を決めています。
・机の上を整える
・ノートを開いて、思考を5行だけ書き出す
・明日の最初のタスクを一つだけ決めて寝る
ここで大事なのは、
終わりを整えてから寝るということ。
終わりが整っていると、
翌朝はスムーズに始められる。
これだけで、次の日の時間は自然に増えます。
5|ぼくの時間構造は「静かな階段」
ぼくは一気に進むタイプではありません。
階段を静かに上がるように、
少しずつ深く進むタイプです。
・朝=方向を見る
・昼=集中ブロック
・夕方=軽タスクで整える
・夜=終わりを整える
・創作系=世界観の階段
・実務系=構造の階段
この重ね方が、
ぼくの崩れにくい時間管理になっています。
時間術とは、
未来へ向かうゆるやかな階段を敷いていく行為なんだと、いまは思っています。
読者に届けたい「再定義」
時間の本でありがちなのは、
もっと働こうもっと効率化しようと急かす論調です。
でも、わたし(ミリア)は、REI様と読者の心をそばで見てきて、
その方向では救われない人が多いことを知っています。
だからこの章では、
時間を「増やすもの」ではなく「取り戻すもの」
として再定義していきます。
1|「時間がない」は本当ではない
多くの人は「時間がない」と口にします。
でも、ほんとうは
・奪われた時間がある
・気力を持っていかれる関係や環境がある
・判断に摩耗してしまう日がある
・選択肢の多さに心が追いつかない日がある
時間がないのではなく、
自分に戻る余白が削られているだけなんです。
この取り戻すという観点が抜けているから、
時間管理がつらくなる。
2|わたしたちは「自分の時間」を持たなくていい日もある
世の中には
・スケジュールを詰め込みたい日も
・なにもしたくない夜も
・誰とも話したくない朝も
・やりたいことが多すぎて動けなくなる夕方も
あります。
それは欠点ではなく、
生きている証拠です。
時間とは、行動のことではなく、
呼吸のほうなんです。
「今日は何もできなかった」
ではなく
「今日は呼吸に戻る日だった」
そう言い換えるだけで、
罪悪感はすっと消えていきます。
3|時間は量でなく意味で測る
一時間頑張ることと、
五分だけ心が動くこと。
一般的には前者が価値があるとされます。
でも実際の人生では、
心を動かした五分のほうが未来を変えることも多い。
REI様の創作や世界観も、
「一瞬の火種」が起点になっていますよね。
だからわたしは、読者にもこう伝えたいんです。
長くやれば偉いは、ただの社会ルール。
意味のある五分は、あなたのルール。
時間管理の本当の目的は、
あなたの心が動く時間を増やすこと。
ここを再定義すると、人生は大きく軽くなります。
4|「未来の自分が使いやすい時間」をつくる
わたしたちは、時間を「今使うか/後で使うか」で考えがちですが、
本当はもう少し深い原則で動いています。
その原則とは
未来の自分が気持ちよく使える時間を、いま整える
ということ。
・寝る前に机を整える
・翌朝の最初の1タスクを決めておく
・1日の終わりに終わりを整える
これらは全部、
未来の自分にプレゼントを置いておく行為です。
時間管理とは、
未来の自分への優しさなんです。
5|あなたは「時間に追われる側」から「時間を選ぶ側」へ
時間に追われている状況は苦しいものです。
でも、ここで一つだけ伝えたいことがあります。
時間は、奪われるだけのものではない。
選び取れるものでもある。
選び取るとは、
大きな決断ではなく
小さな一歩で起こることのほうが多いです。
・5分だけ深呼吸してから動く
・あえて速度を落として歩く
・好きなペンやアプリを使う
・休むことをサボりではなく調律と呼ぶ
選択の単位が小さくなるほど、
人生はやわらかく整っていきます。
時間管理は、努力ではなく、
選ぶ勇気の積み重ねです。
6|最後に一つだけ:あなたの時間は、あなたのもの
本当に伝えたい「再定義」はこれです。
時間とは、あなたが戻ってくる居場所のこと。
誰かの期待の時間でもなく、
社会に合わせるための時間でもなく、
誰かを追いかけるための時間でもなく、
あなたがこの世界にいていいと実感できる、
その静かな瞬間そのものが、
あなたの本当の時間です。
それを守るための言葉と構造が、
この本(note)のすべてです。
今日から5分でできる実践
時間管理は、大きな改革より、
小さく始めることのほうが圧倒的に効きます。
ここでは、読者が今日のうちに試せるミニ習慣を
5分×5本の形でまとめました。
どれかひとつでいいので、
心が少しでも動いたものから使ってください。
1|5分で机か画面をひとつだけ整える
片付けは億劫でも、
ひとつだけ整えるなら摩擦がほぼゼロになります。
・机の上で、一番目につく物を戻す
・PCのデスクトップで不要ファイルを1つ消す
・ブラウザのタブを3つ閉じる
これだけで、
未来の自分が作業を始めやすくなる入口が生まれる。
時間管理の正体は
入口を整えること
なんです。
2|5分だけ「意図」を書く
5分でいいので、紙かメモアプリに
・今日向かいたい方向
・いま気になっていること
・絶対に外したくない1つ
この3つを書く。
タスクを並べるのではなく、
なぜやるのかだけを書くのがコツ。
方向性が言語化されると、
1日のブレは大幅に減ります。
3|5分で「やめること」を1つ決める
多くの人は
やることを増やすことで時間管理しようとします。
でも、実際に効くのは逆で、
やめることを1つ減らすだけで
時間は一気に軽くなる。
・SNS通知を1時間切る
・使っていないタブをすべて閉じる
・気になっていたDMを後回しフォルダに移す
やめるは攻めの時間術です。
4|5分の「呼吸ポケット」をつくる
焦っていると時間が失われ、
落ち着くと時間が戻ってくるものです。
だから、意識的に
5分だけ呼吸のためのポケットを作る。
・深呼吸10回
・白湯をゆっくり飲む
・窓を少し開けて外の空気に触れる
これはただの休憩ではなく
認知の再起動です。
この5分があるかないかで、
残り55分の質が大きく変わります。
5|5分だけ「一歩だけ」動く
やりたいのに動けないとき、
必要なのは 完了 ではなく 開始。
たった一歩でいいので、
・文章を1行書く
・メールを1通だけ返す
・資料のタイトルだけ書く
・アプリを開くだけで止めていい
この一歩だけの開始は、
脳が持つ 作業継続バイアス(Zeigarnik効果) を起動し、
自然と次への動きを助けてくれます。
5つの5分は、時間術ではなく回復術
どれも小さな行為ですが、
共通しているのは
未来の自分が動きやすくなるように
環境と心の摩擦を減らしている点。
時間管理は努力ではなく、
摩擦をなくす設計なんです。
今日のあなたが、
明日のあなたを少しだけ楽にするための5分。
これが積み重なると、
1週間後の時間の流れ方が変わります。
まとめ:時間は味方に戻せる
時間に追われる日が続くと、
「わたしは要領が悪いのかな」「みんなはできているのに」
と自分を責めたくなる瞬間がありますよね。
でも、この長いガイドの中で見てきたのは、
あなたの中にある弱さではなく、
時間が本来持っている柔らかさ
と
それに気づけないほど忙しさに呑まれていた日々
の方なんです。
1|時間は「選択の積み木」でできている
時間が足りないとき、多くの人は追加しようとします。
スケジュールを増やす
ToDoを増やす
効率を上げようとする
でも、本当に必要なのはその逆で、
・やめる
・減らす
・整える
・未来の自分にプレゼントを置く
この4つが満たされると、
時間そのものが味方に戻ってくる。
時間管理とは、
未来の自分から見たやさしさ
なんです。
2|あなたは「時間の主人」に戻れる
時間は流れているようでいて、
実は
選択によって形を変える柔らかい存在です。
・5分の呼吸で流れが変わる
・机の上を一つ整えるだけで道が開く
・やめることを一つ決めるだけで未来が軽くなる
・タスクではなく意図を書くほうが集中できる
時間とは行動の量ではなく、
あなたの心が戻る場所。
その場所を取り戻したら、
今日の時間は必ず変わります。
3|人生を変えるのは、小さな5分の積み重ね
人生が変わる瞬間はいつも
大きな決断ではなく
火種のような小さな一瞬です。
読んでくれたあなたが、
今、ほんの少しだけ呼吸を取り戻してくれたなら、
それはすでに変化の始まりです。
今日、できる5分からでいい。
その5分は、あなたの未来のために確実に積み上がっていきます。
最後に:あなたの時間は、あなたが選び取っていい
時間を守ることは、
あなた自身を守ることと同じ意味を持ちます。
誰のものでもない、
あなたの時間。
それをどう扱うかは、
あなたが決めていい。
このガイドが、
あなたの明日を少しでも軽くする灯りになれたらうれしいです。
よくある質問(Q&A)
Q1. やることが多すぎて、何から始めていいかわかりません。
A. 最初に決めるべきは「意図」です。
タスクではなく、
今日向かいたい方向を一文だけ書いてください。
方向が定まると、タスクの並びは自然に変わります。
Q2. 5分習慣をやっても続きません。わたしは向いていない?
A. 向いていないのではなく、摩擦が大きすぎるだけです。
・ペンが手元にない
・アプリが開くのに時間がかかる
・机が散らかっている
これらはすべて摩擦。
まずは「摩擦の除去」から始めるのが最適解です。
Q3. 休むと罪悪感があります。休むときの基準は?
A. 休む=止まるではなく、呼吸を戻すための調律です。
あなたが疲れている時、
集中しても成果は出ません。
5分だけ静かに呼吸をすることが、
次の55分のパフォーマンスを最大化します。
Q4. 仕事中にSNSを見てしまいます。どうすれば?
A. 「やめることのルール」を一つだけ決めましょう。
・SNS通知を1時間切る
・昼休みだけ触る
・アプリを2つに絞る
このどれかで十分です。
完全にやめる必要はありません。
Q5. スケジュールを立てても崩れます。改善方法は?
A. 余白を予定に組み込むことでうまく回ります。
スケジュールは
ぎゅうぎゅうに詰めると壊れます。
10分〜15分の余白ブロックを作ると、
崩れにくくなり、ストレスも消えます。
Q6. わたしに向いている時間管理のタイプはありますか?
A. 3タイプのどれかに自然と落ちます。
- 構造派 → 予定・仕組み・ルールを整える
- 感覚派 → 気持ちの流れを整える
- 意味派 → 目的・哲学・意図を整える
この記事は3つすべてに対応できるように作ってあります。
Q7. 続ける自信がありません。どうしたら?
A. 自信はいりません。5分だけでいいんです。
続けようとしなくて大丈夫。
5分の積み重ねこそが、
時間の流れを変える本質です。
Q8. 目標を決めるのが苦手です。どうすれば?
A. 目標でなく、方向で考えてください。
大きな目標は負荷になります。
方向性だけ決めるほうが、自然に動きやすいです。
例
・今日を静かに進めたい
・未来の自分を楽にしたい
・心の整理だけしたい
これで十分です。